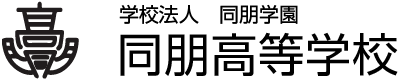ニュースNEWS
同朋オープン・フォーラムを開催しました【実行委員会】
29回目となる同朋オープン・フォーラムを「これってどうなの?」~価値観を交流させて見えてくるもの~をテーマに置き、本校ホールおよび各教室を会場に開催しました。
同朋オープン・フォーラムとは、「同朋の教育」を生徒・保護者・教職員ときには市民を交えて意見交換し、それを今後の学校教育に活かす取り組みです。
今回も約170名もの生徒・保護者の方にお集まりいただき、教職員と一緒になって20の分散会グループで意見交換することができました。
いただいたご意見・ご感想・ご提案を、今後の同朋の教育に活かすことができるよう、関係部署で協議してまいります。
|
助言者:名古屋造形大学 大橋基博先生によるご講評 みなさんこんにちは。名古屋造形大学特任教授の大橋です。 同朋高校って、「ちょっと変わった学校」なんです。言ってしまえば「変な学校」なんです。みなさんニュースを見られました?同朋高校は学校を12日間使って「名古屋平成中村座」をやるんですよ。これって、考えられます?普通でしたら、PTA会長だとかが校長室に乗り込んで「校長は何を考えているんだ」となってもおかしくない案件なんですよ。でも、誰もそんなことをしていないでしょ?それよりも「校長は良い決断をした」と褒めてしまう学校なんです。つまりこれは、学校の雰囲気が非常に良いということなのです。普通の学校だったらできないことができてしまう。私個人的には、前回の中村座同朋公演を観ましたので、また観に行きたいと思っています。
保護者の方からすると、地域懇談会だとか、○○フェスティバルなど、保護者の方が関わる行事がいっぱいありますよね。「子供を入学させたつもりが、親も入学してしまった」これが同朋高校なのではないかと思います。これは、同朋高校独自に学校を良くしていこうとする歴史があるからなのです。学校というと、生徒と先生との関係が中心になりがちですが、同朋高校の場合は、生徒と先生と保護者さらには地域とが結びついて教育活動を展開してきたというのが大きな特色だと思います。保護者のみなさんの中で、公立高校に子供を通わせた方の場合は、公立高校と同朋高校とを比較してみてください。学校の雰囲気が全然違うと思います。これは、同朋高校が生徒だけではなく、保護者との結びつき、地域との結びつきを、フォーラムなどの形で学校づくりにまで発展させているからです。これが同朋高校の大きな強みではないかと思います。
「学校づくり」というと難しいことのように思えますが、これは子供の要求や、保護者や地域の要求に応える教育を実現する。そのために学校関係者が努力するということです。学校というのは、先生だけでは教育活動ができません。先生を支えるために保護者や地域がいます。さらには、先生のお尻を叩く保護者の力がいるのです。そうすることで、先生はもっともっと頑張ろうという姿勢になります。同時に、そういう環境にいる生徒は、「自分たちももっと頑張らなきゃいけない」という自覚を持つことにつながります。それができるのが、同朋高校なのではないでしょうか。それを具体化させたものが、このオープン・フォーラムなのではないでしょうか。
同朋高校のオープン・フォーラムとは、生徒と保護者と教員とときに市民との四者が集まって、教育や子育てを考える四者協議会というものです。これが大きな特徴です。同朋高校は全国に先駆けてフォーラムを開き、それを地域にも開いてきました。全国にも三者協議会や四者協議会を開いている学校があります。有名な学校として、長野県の公立高校に三者協議会を開いている学校があります。この学校に関する本は、何冊も出版されています。それに続いて有名なのが、東京都の私立高校が四者協議会を開いています。つい先日、四者協議会がおこなわれたそうです。そして同朋高校のフォーラム。いま、この会場にざっと150人ほどがいるのでしょうか?これだけの規模でおこなっている学校はそれほどありません。長野県の高校は20~30人ほど。愛知の公立高校でいくつか取り組んでみた学校があるのですが、そこでも10~20人くらいです。だから、同朋高校の取り組みの凄さが分かりますよね。ちなみに、東京の高校は体育館で350人ほどの規模でやっていましたが、同朋高校はそれに次ぐ規模ではないかと思います。そして、協議会の歴史を調べると、長野の高校は1997年から取り組みが始まりました。東京の高校は2003年にはじまりました。同朋高校は1994年からはじまっています。歴史が古く、これほどの規模でおこなっていることは誇っていいことです。こういう場があるというのは全国的にも珍しいことです。
先ほどの分散会では、生徒さんが意見を言う。それに対して先生が意見を言い、保護者も意見を言う。同朋高校では当たり前の光景ですが、全国的には全然当たり前ではありません。それができるというのは、自慢していいことです。これは、「子供の意見表明権」の保証であるとも言えます。意見表明権というのは、意見を表明するだけではなくて、それを大人が適切に受け止めて、実現させなくてはいけません。だから、こうしたフォーラムを学校がおこなうということは、学校が、先生が強い覚悟を持っているということです。意見を聞いて無視をしたら、大変なことです。生徒からしたら、教員不信、学校不信になります。でも、こういった会をやるということは、生徒の意見をちゃんと聞いて、できるだけ取り入れるぞという決意があるからやれるということ。ですから、生徒のみなさんも先生たちの覚悟というものをきちっと評価していただきたいなと思います。そして、それに応えるために、生徒も頑張らなくちゃいけない。こういったWin-Winの循環関係ができるということが重要ですから、生徒の責任も大きいということ。こういった会があるというのは、先生たちからすると大変なことですが、生徒も頑張るんだ、努力するんだという気持ちでやっていっていただきたいです。
今日の議論を見ていると、アットホームな分散会で意見が言えたと思います。ただ分散会では、そのグループの中だけで話が終わってしまいます。ですから先生方にお願いしたいのは、それぞれの分散会で出た意見を集約して、次にどうするのか、生徒の意見・保護者の意見を反映させる取り組みをしていただきたいです。「生徒が学校の主人公になる」「自分たちの意見がきちんと反映される」という成功体験がきちんと積み重ねられるということ。これが非常に重要です。日本の若者・高校生は自己肯定感が低いと言われています。これは、自分たちが何か言っても、大人がそれを聞いてくれないから、何をやっても駄目だと落ち込んでしまうのです。ですが、意見が言え、それを受け入れてくれる。時に受け入れられないこともありますが、それについて理由を大人がきちんと説明してくれることで、高校生は自己肯定感を持って、民主主義の主役となって、社会をよくする主体に繋がると思います。
コロナ禍でこれまで同朋高校のフォーラムに参加できませんでしたが、今年はこうして参加でき嬉しく思っています。どうも今日はありがとうございました。 |