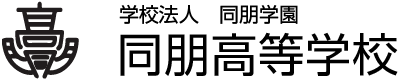同朋について同朋オープン・
フォーラム
同朋オープン・フォーラムは、もともと新しい同朋の教育をみんなで考えようという生徒・保護者・教職員からなる有志実行委員の集まりから生まれたものでした。
学校は生徒が主人公であり、その学校は生徒・保護者・教職員の三者で作るものです。
毎年6月から7月に実施される地域懇談会で出されたさまざまな意見、生徒会や教員から見える課題や期待の中からテーマを設定し、そのテーマにふさわしい全体会・分科会を生徒・保護者・教職員の三者で構成された実行委員会で議論を重ね、フォーラムの準備と運営を行っています。その時々に設定される教育づくりの課題に対して、三者(時には市民を交えて四者)でさまざまな観点からそれぞれの立場で、「同朋の教育」について議論し、その中から次へのステップになるヒントを見つけ出していくのがこの フォーラムの目的なのです。
そのため2011年度より、これまでの「同朋教育フォーラム」という名称から、親しみやすい「同朋オープン・フォーラム」に名称を変更しました。
この間のフォーラムから見えてきたのは、生徒たちにとって「自身の手で将来の道を切り拓く」「自主自立の精神を身につける」ことが大きな課題となっていることです。こうした問題点を生徒・保護者・教職員の三者(時には外部の力を借りて四者)で議論し合うのが同朋オープン・フォーラムです。



| 第1回1994年 | 「父母と生徒と教師による同朋の教育を考える集い」 |
|---|---|
| 第2回1995年 | 「同朋の教育改革の扉を開けるのは三者」 |
| 第3回1996年 | 「親と生徒、教師による“一言云いたいことがある” ~親の言い分、子供の言い分、教師の言い分~ 」 |
| 第4回1997年 | 「制服問題に学校提案 熱い討論の3時間」 |
| 第5回1998年 | 「自分を好きになること すべてはそこから」 |
| 第6回1999年 | 「みんなで話そう、何でも聞こう! 子育て、子ども、学校…のこと」 |
| 第7回2000年 | 「みんなで話す、みんなの同朋」 |
| 第8回2001年 | 「生徒・父母・教師・市民で 学ぼう・話そう・考えよう 新しい教育楽しい授業」 |
| 第9回2002年 | 「子どもたちを・家庭を・同朋をもっとステキに」 |
| 第10回2003年 | 「『豊かな学力への挑戦』で見つけたもの」 |
| 第11回2004年 | 「今をどのように学び、教え、生きるか ~現代社会と学校の役割~ 」 |
| 第12回2005年 | 「みんなで出し合って、考え合えるって素晴らしい!」 |
| 第13回2006年 | 「地域に飛び出し、地域のコミュニティーづくりに貢献しよう」 |
| 第14回2007年 | 「高校生にとって必要な学びとは?身なりとは?」 |
| 第15回2008年 | 「聞ける!話せる!!わかり合える!!!」 |
| 第16回2009年 | 「同朋発→近所のしゃべり場経由→悩みゼロ行き」 |
| 第17回2010年 | 「みんなでつくる明日の同朋」 |
| 第18回2011年 | 「話せば分かる・話せば変わる」 |
| 第19回2012年 | 「未来を見つめて ~成長する生徒・親・先生・学校~ 」 |
| 第20回2013年 | 「話す・伝える・考える ~現実・その先の未来へ~ 」 |
| 第21回2014年 | 「大切なのは話し合うこと ~私たちの声で作る学校~ 」 |
| 第22回2015年 | 「子供たちの未来をソウゾウしよう ~18歳を大人にするために 大人が力を合わせよう~ 」 |
| 第23回2016年 | 「頼りになる仲間 同朋ファミリー ~大人になるためのステップ つなげよう未来に~ 」 |
| 第24回2017年 | 「頼りになる仲間 同朋ファミリー ~語り合おう、無限の可能性(みらい)~ 」 |
| 第25回2018年 | 「頼りになる仲間 同朋ファミリー ~これからの同朋の教育に期待するもの 過去から未来へ~ 」 |
| 第26回2019年 | 「頼りになる仲間 同朋ファミリー」 |
| ※2020年 新型コロナウイルス感染症対策として中止 | |
| 第27回2021年 | 「頼りになる仲間 同朋ファミリー ~最幸の人生の見つけ方~ 」 |
| 第28回2022年 | 「頼りになる仲間 同朋ファミリー ~最幸の人生の見つけ方~ 」 |
| 第29回2023年 | 「『これってどうなの?』~価値観を交流させて見えてくるもの~ 」 |
| 第30回2024年 | 「みんなはどうしてる?~本当は聞いてみたかったこと~ 」 |
| 第31回2025年 | 「つながろう、ひろげよう 同朋ファミリー ~三者(四者)でつくる「同朋」のミライ~ 」 |